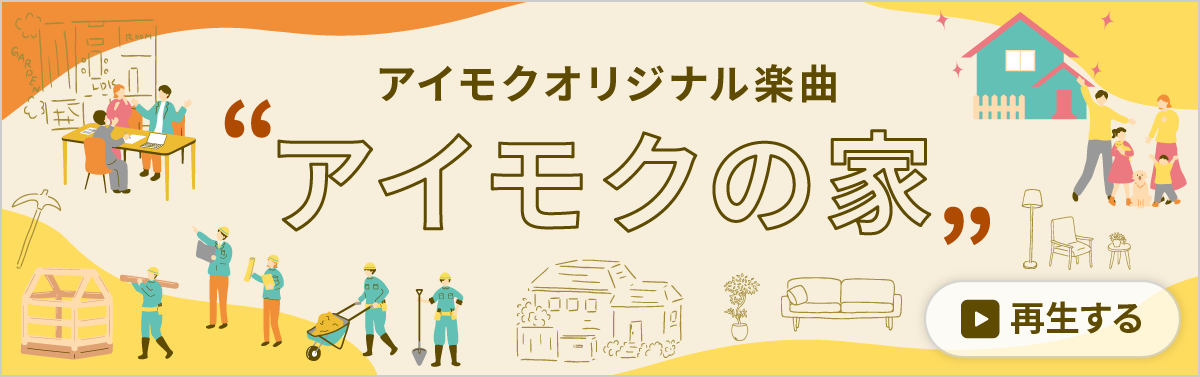「耐震等級3」は当たり前?潜む“2つの基準”という落とし穴
岐阜県恵那市周辺で、ご家族の未来を守るためのマイホームをご検討中の皆様。「地震に強い家」を考えたとき、多くの方が「耐震等級3」というキーワードを一つの安心材料にされていることでしょう。近年、多くの住宅会社がこの最高等級を標準仕様として掲げるようになり、「耐震等級3は当たり前」という風潮さえ感じられます。
しかし、もしその「耐震等級3」という言葉の裏側に、信頼性を大きく左右する“2つの異なる基準”が存在することをご存知でしょうか。同じ「耐震等級3」というお墨付きを得ていても、その根拠となる計算方法によって、建物の安全性の証明レベルには大きな隔たりがあるのです。
この記事では、住宅の耐震性能の本質を見極めるために不可欠な「構造計算」に焦点を当て、なぜ「耐震等級3」という言葉だけでは不十分なのか、その理由を専門家の視点から深く、そして分かりやすく解説していきます。皆様の大切な家づくりが、本当の意味での安心・安全につながるための一助となれば幸いです。
なぜ今、「耐震等級3」が標準仕様になりつつあるのか
そもそも「耐震等級」とは、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき定められた、建物の地震に対する強さを示す指標です。等級1は建築基準法で定められた最低限の耐震性能、等級2はその1.25倍、そして等級3は1.5倍の強度を持つことを示します。
過去に発生した阪神・淡路大震災や熊本地震などの大規模な地震では、建築基準法レベル(等級1相当)の建物に倒壊・全壊の被害が見られた一方で、一部の調査では、耐震等級3の住宅は被害が少ない傾向が確認された事例があります(例:熊本地震の一部調査)。ただし被害程度は地域や設計・築年等により差があるため、一概に「無被害」とは言えませんが、安全性を高める上で重要な等級であることは間違いありません。こうした教訓や、マイホームへの安心・安全を求めるお客様の意識の高まりを受け、多くの住宅会社が「耐震等級3」を標準仕様として採用するようになりました。これは、家づくりにおける安全基準が、社会全体として引き上げられている証拠と言えるでしょう。
要注意!同じ等級でも信頼性が異なる「壁量計算」と「構造計算」
しかし、ここで注意すべき重要な点があります。それは、耐震等級3を取得するためのルートが、大きく分けて2つ存在するということです。
- 壁量計算(仕様規定):簡易的な計算方法
- 許容応力度計算(構造計算):詳細な計算方法
「壁量計算」は、主に木造2階建て以下の住宅で用いられる簡易的なチェック方法です。一方で「構造計算」は、鉄骨造や3階建て以上の木造住宅では義務付けられている、より精密で科学的な検証方法です。
驚かれるかもしれませんが、現在の法律では、多くの木造2階建て住宅は詳細な「構造計算」を行う義務がありません。そのため、同じ「耐震等級3」を謳っていても、簡易的な「壁量計算」で済ませているケースと、一棟一棟精密な「構造計算」を行っているケースが混在しているのが実情です。この違いが、万が一の大地震の際に、建物の振る舞いに大きな差を生む可能性があるのです。
【徹底比較】壁量計算と構造計算、何がどう違うのか?
では、「壁量計算」と「構造計算」では、具体的に何が違うのでしょうか。ここでは、それぞれの計算方法が何を検証しているのかを比較し、なぜ私たちが構造計算を重視するのか、その理由を解説します。
壁の量だけで判断する「壁量計算」
壁量計算は、その名の通り「地震や風の力に耐えるための壁(耐力壁)が、建物の床面積に対して十分な量だけ、バランス良く配置されているか」をチェックする方法です。
具体的には、建物の重さや床面積から必要な壁の量を算出し、それが基準を満たしているかを確認します。柱の太さや、地震時に柱が土台から引き抜かれないようにする「柱頭・柱脚の接合方法」なども簡易的なチェック項目に含まれますが、あくまで仕様規定に沿った確認が中心です。
この方法は、一定の耐震性を確保するための最低限のルールであり、建物全体にかかる複雑な力の伝わり方や、梁や基礎といった構造部材一つひとつにかかる負荷までは詳細に検証しません。いわば、家の安全性を「壁の量」という一面から見た簡易チェックと言えるでしょう。
家全体を科学的に検証する「構造計算(許容応力度計算)」
一方、「構造計算(許容応力度計算)」は、壁量計算とは比較にならないほど緻密で、建物全体を一つの構造体として捉え、科学的に安全性を検証するプロセスです。
地震や台風、積雪といった自然の力が加わった際に、建物の基礎、柱、梁、床、屋根といったあらゆる部材に「どのような力が、どれくらいかかるのか」を一つひとつ計算します。そして、その力に対して部材が変形したり、破壊されたりすることなく、十分に耐えられるかどうか(=応力度が許容範囲内か)を検証します。
さらに、建物全体の変形量や、地震時に建物がねじれないか(剛心と重心のバランス)、強風で建物が浮き上がらないかなど、多角的な視点から安全性を徹底的にチェックします。これは、いわば「家の構造に関する健康診断」のようなものです。見えない部分の負荷まで数値で証明することで、初めて科学的根拠に基づいた安全性が確保されるのです。
2025年法改正で変わる!構造計算が必須の時代へ
これまで、床面積500㎡以下の木造2階建て住宅などは「4号建築物」と呼ばれ、建築確認の際に構造計算書の提出が不要となる「4号特例」という制度がありました。これが、多くの木造住宅で構造計算が省略されてきた背景です。
しかし、住宅の安全性をさらに向上させるため、2025年4月1日に建築基準法が改正され、この4号特例が縮小されることになりました。
この法改正により、これまで特例の対象だった多くの木造2階建て住宅でも、構造に関する仕様規定への適合、あるいは構造計算が求められるようになります。これは、国全体として住宅の安全基準を「構造計算」を基本とする方向へ引き上げようとしている明確なメッセージです。つまり、これからの家づくりにおいて、詳細な構造計算はもはや特別なことではなく、必須の条件となっていくのです。
参考:住宅:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
愛岐木材住建が採用するパナソニック「テクノストラクチャー工法」
私たち愛岐木材住建は、ここ東濃地域で長く家づくりに携わる中で、お客様に「心からの安心」をお届けするためには、法律で定められた基準をクリアするだけでは不十分だと考えてきました。だからこそ、私たちはパナソニックの耐震住宅工法「テクノストラクチャー」を選んでいます。詳しくは「テクノストラクチャーとは?地震に強い家の仕組みをプロが解説」でも解説していますが、この工法は、まさに科学的根拠に基づいた安全性を追求するための最適な答えなのです。

全棟で「構造計算」を実施するのは、私たちの最低基準です
愛岐木材住建が手掛けるテクノストラクチャーの家は、たとえ法律で義務付けられていない木造2階建ての住宅であっても、原則として全棟で詳細な「構造計算(許容応力度計算)」を実施し、その構造計算書をお客様にご提出しています。
これは、私たちにとって特別なことではありません。お客様の命と、大切なご家族との未来をお預かりする者として、絶対に譲ることのできない最低基準です。壁量計算のような簡易的なチェックではなく、一棟一棟、その家の間取りや形状に合わせて精密な構造計算を行うこと。それが、私たちの家づくりの第一歩であり、お客様への誠実な姿勢の証だと考えています。
木と鉄の複合梁「テクノビーム」が実現する強靭な構造
テクノストラクチャー工法の最大の特徴は、木と鉄の複合梁「テクノビーム」にあります。これは、住宅の梁として最も重要な部分に、軽量でありながら鉄骨に匹敵する強度を持つH形鋼を、集成材で挟み込んだ独自の部材です。
木の家は温かみがある一方で、長い年月の中で梁がたわみやすいという性質も持っています。テクノビームは、この木の弱点を鉄の力で徹底的に補強することで、一般的な木造住宅をはるかに上回る構造強度を実現します。この強靭なテクノビームがあるからこそ、柱の少ない広々としたリビングや大きな吹き抜けといった、自由度の高い間取りを、耐震性を一切犠牲にすることなく実現できるのです。そして、この強固な骨格が、次にご紹介する「災害シミュレーション」という、さらに一歩進んだ安心を可能にしています。
構造計算の先へ。一棟ごとの「災害シミュレーション」という安心
一般的な構造計算は、いわば静的な状態での強度計算です。建物に一定の力がかかった際に、部材が耐えられるかどうかを検証します。しかし、実際の地震は、複雑で断続的な「揺れ」として建物を襲います。
そこでテクノストラクチャーでは、全棟で実施する構造計算に加え、さらに一歩踏み込んだ「災害シミュレーション」を行っています。これは、一般的な構造計算とは次元の異なる、より現実に即した動的な検証プロセスです。このシミュレーションは、私たちがご提供する安心を支える、重要な根拠の一つです。

あなたの家を3Dで再現。388項目で地震の揺れを徹底検証
テクノストラクチャーの災害シミュレーションは、お客様からお預かりした一棟一棟の設計プランに基づき、コンピューター上に精巧な3Dモデルを作成することから始まります。それは、いわばデジタル空間に建つ「あなただけの家」です。
このモデルに対し、地震や台風、豪雪といった、その地域で起こりうる様々な自然災害の力を加え、建物がどのように変形し、どの部材にどれくらいの負荷がかかるのかを徹底的に解析します。パナソニックの技術資料によれば、そのチェック項目は実に388項目にも及びます。この国の基準をはるかに超えるパナソニック独自の厳しい基準をすべてクリアしなければ、私たちは次の設計・施工プロセスに進むことはありません。この緻密な検証こそが、机上の計算だけでは見抜けない、潜在的な構造上の弱点を洗い出し、より安全な家へと昇華させるための重要なプロセスなのです。
震度7クラスの揺れを再現し、倒壊・損傷リスクを可視化
災害シミュレーションでは、過去に日本で発生した阪神・淡路大震災や熊本地震など、実際に観測された震度7クラスの地震波データを再現。その強烈な揺れを、あなたの家の3Dモデルに与えることで、万が一の事態を限りなくリアルに予測します。
シミュレーションの結果は、建物のどの部分に力が集中するのか、柱や梁がどの程度たわむのか、接合部に過度な負担はかからないか、といった情報を色分けなどで「可視化」します。これにより、私たちは構造上のウィークポイントを事前に特定し、梁のサイズを太くしたり、補強金具を追加したりといった最適な対策を講じることができます。
これは、単に「耐震等級3です」と言うのとは全く意味が異なります。「震度7クラスの揺れをシミュレーションした結果、この設計で安全性が確認できました」と、科学的な根拠を持って断言できること。これこそが、愛岐木材住建がテクノストラクチャーでお届けする、究極の安心なのです。
まとめ:恵那市で本当に地震に強い家を建てるために
今回は、「耐震等級3」という言葉の裏に隠された重要な事実と、本当の意味で地震に強い家を建てるための「構造計算」、そしてさらにその先にある「災害シミュレーション」の重要性について解説しました。
【本記事のポイント】
- 「耐震等級3」には、簡易的な「壁量計算」と、詳細な「構造計算」の2つのルートがある。
- 「構造計算」は、壁だけでなく建物全体の部材一つひとつにかかる力を科学的に検証するため、信頼性が格段に高い。
- 2025年の法改正により、今後は構造計算が家づくりのスタンダードになっていく。
- 愛岐木材住建が採用するテクノストラクチャーは、全棟で構造計算を実施した上で、さらに一棟ごとの「災害シミュレーション」を行い、震度7クラスの揺れに対する安全性を可視化・検証している。
家は、ご家族の命と財産、そして未来を守るための大切な器です。だからこそ、私たちは「等級」という言葉だけに頼るのではなく、その一棟一棟が科学的根拠に基づいた、確かな安全性を備えていることを証明する責任があると考えています。
私たち愛岐木材住建は、岐阜県恵那市を含む東濃地域に根ざし、土地探しから設計、施工、そしてアフターサポートまで、お客様の家づくりにワンストップで寄り添います。もし、ご自身の家づくりにおける耐震性について、少しでもご不安な点や、さらに詳しく知りたいことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。専門のスタッフが、皆様の疑問に一つひとつ丁寧にお答えいたします。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。